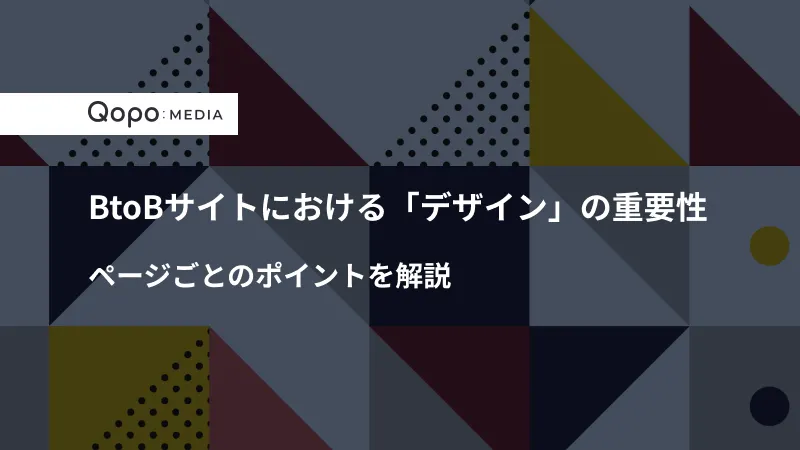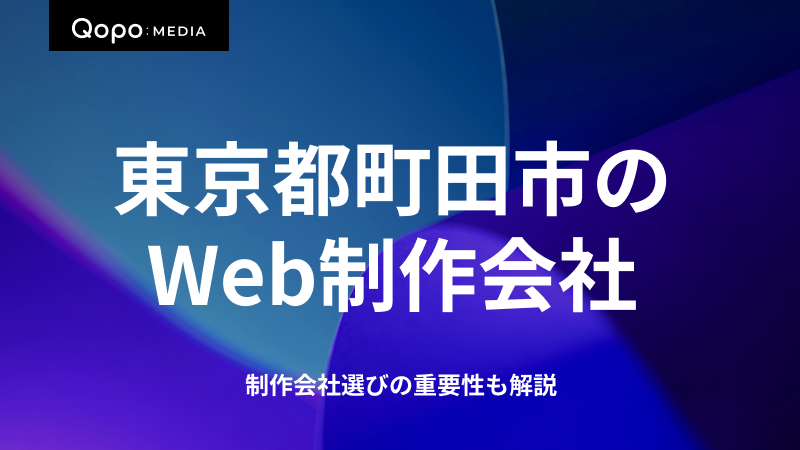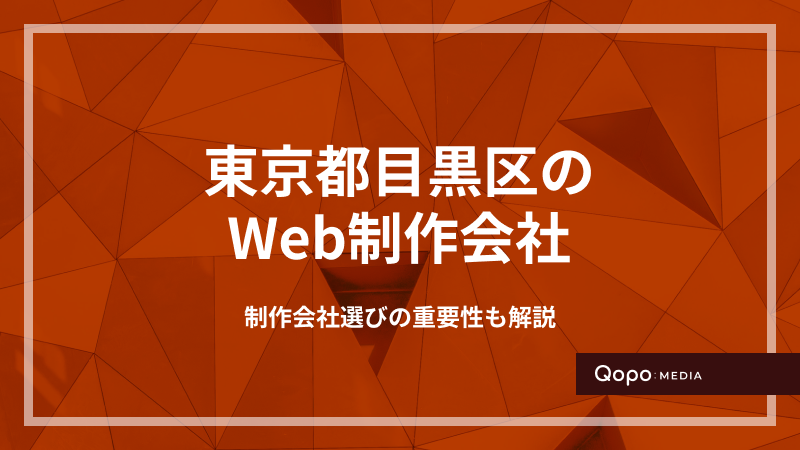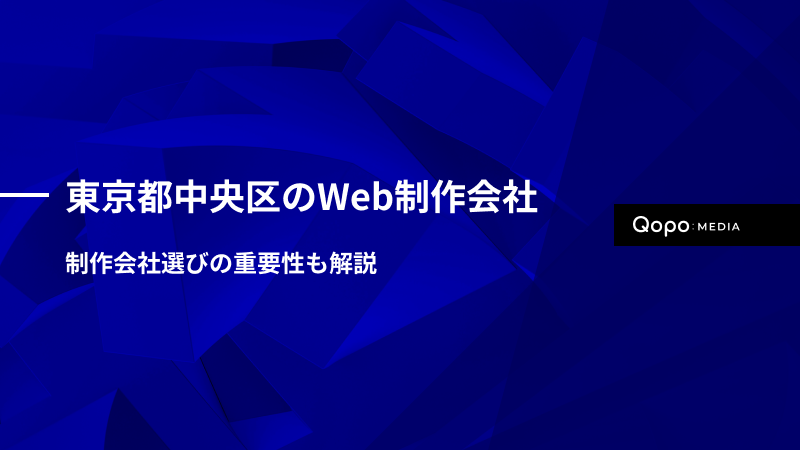BtoBサイトにおける「デザイン」は、単なる「見た目の良さ」を指す言葉ではありません。ビジネスの成果を最大化するために、設定した戦略を具体的な形に落とし込み、成果へと変換する仕組みそのものです。多くの意思決定者が関与し、長期的な検討が必要となるBtoBでは、顧客の課題解決を支援し、信頼を獲得するための論理的なデザインが不可欠です。
本記事では、BtoBサイトのデザインがなぜ重要なのか、その根幹となる考え方を解説するとともに、トップページからお問い合わせ完了ページまで、主要なページごとにデザインのポイントを具体的にご紹介します。
目次
BtoBサイト制作における「デザイン」の重要性
BtoBビジネスにおけるWebサイトは、企業の顔であり、見込み顧客との最初の接点となる重要なチャネルです。ここでは、なぜBtoBサイトにおいてデザインが重要視されるのか、その理由をBtoCサイトとの違いや戦略との関連性から掘り下げていきます。
BtoCサイトとの違いを認識する
BtoBサイトのデザインを考える上で、まずBtoCサイトとの根本的な違いを理解することが重要です。個人の感情や衝動的な購買が起こりやすいBtoCに対し、BtoBの購買プロセスは「合理的・長期的・複数人での合意形成」という特徴があります。 検討者には経営層から実務担当者まで様々な立場の人物が混在し、それぞれが異なる評価軸で情報を探しています。
そのため、デザインは装飾的な美しさよりも、情報が探しやすく、理解しやすく、信頼できる「可読性」「再現性」「信頼性」が最優先されます。サイト訪問者が抱える課題に対し、ベネフィット、その根拠、そして詳細情報というように、深く掘り下げられる層構造のコンテンツ設計がUX(ユーザー体験)を大きく左右します。
関連記事:BtoBサイトとは|データで見る「成功企業がサイトを重視する理由」
サイトの「戦略」を設計する
優れたBtoBサイトのデザインは、必ず明確な事業戦略に基づいています。デザインは戦略を実現するための「器」であり、制作に着手する前に、サイトを通じて「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを定義することが成功の鍵となります。 まずは、問い合わせ数や資料ダウンロード数、商談化率といった具体的な事業目標(KGIやKPI)を設定します。
次に、製品の機能や特徴を「顧客の工数削減」や「売上への貢献」といった提供価値(ベネフィット)に翻訳し、顧客の検討プロセス(課題認知→比較検討→稟議)の各段階で必要な情報をマッピングします。この戦略設計が、デザインの判断基準となり、関係者間の認識のズレを防ぎ、一貫性のあるサイト構築を実現します。
戦略をもとに「論理的デザイン」に落とし込む
設計した戦略を、成果につながるデザインへと具体的に落とし込むプロセスが「論理的デザイン」です。これは、サイトの目的(戦略)から、各要素の配置(レイアウト)、ユーザーの操作(インタラクション)に至るまで、すべてが一貫した理由に基づいて設計されている状態を指します。言い換えれば、ページ上のすべての要素が「なぜそこにあるのか」「どんな役割を果たすのか」を戦略から逆算して説明できる状態のことです。
例えば、ファーストビューでは「誰の、どんな課題を、どう解決するのか」が一目で伝わるメッセージを配置し、実績や導入企業ロゴといった客観的な根拠で信頼性を補強します。各ページには「資料ダウンロード」や「問い合わせ」といった主要なCTA(行動喚起)を明確に設置し、関連性の高いコンテンツ(サービス→導入事例、事例→関連資料など)へリンクを繋ぐことで、ユーザーが次に取るべき行動に迷わないよう導線を設計します。情報のかたまりは「悩み→解決策→証拠→CTA」という認知負荷の低い順で構成し、図解や比較表を用いて直感的な理解を促すことが重要です。
BtoBサイト制作のページごとのデザインのポイント
ここからは、BtoBサイトを構成する主要なページを取り上げ、それぞれの役割とデザインで押さえるべき具体的なポイントを解説します。各ページが持つ目的を最大化するための設計を意識しましょう。
1. トップページ
トップページは、サイトの「顔」であり、訪問者が数秒で「自社にとって有益なサイトか」を判断する重要な場所です。ファーストビューでは、企業の提供価値が端的に伝わるキャッチコピーと、最も重要なCTA(資料ダウンロードやお問い合わせなど)を分かりやすく配置します。
ページの構成は「顧客の課題提示 → 解決策の提示 → サービスの特徴 → 導入事例や実績 → 導入までの流れ → CTA」というように、訪問者の思考プロセスに沿ったストーリーで展開し、迷わせない情報設計を心がけます。差別化要素は要点に絞り、数値データや顧客ロゴといった客観的な証拠を添えることで、信頼性を高めます。
2. サービス一覧ページ
サービス一覧ページの目的は、訪問者が提供サービスの全体像を把握し、自身の課題に合ったサービス詳細ページへ最短でたどり着けるように誘導することです。ページ冒頭でサービスのカテゴリ全体を簡潔に説明し、「課題別」「業種別」といった絞り込み機能や検索機能を提供することで、ユーザーの探索負荷を軽減します。
各サービスを紹介するカードでは、サービス名、短い要約、主要なメリットを記載し、詳細ページへのリンクを視覚的に分かりやすくデザインすることが重要です。
3. サービス詳細ページ
サービス詳細ページは、見込み顧客が導入を本格的に検討する、意思決定の核となるページです。ファーストビューで「誰の、どんな課題を、どう解決するサービスか」という要点とCTAを明確に提示します。
本文は、単なる機能の羅列ではなく、顧客が得られるベネフィットを軸にした見出しで構成し、図解や比較表、導入フローの図などを活用して直感的な理解を促進します。また、「料金は?」「導入期間は?」といった顧客の懸念事項をあらかじめFAQとしてまとめておくことで、不安を解消し、信頼を高めます。
4. 料金ページ
料金ページは、顧客の最終的な意思決定を後押しする重要な役割を担います。料金体系(月額制、ライセンス制など)を分かりやすく図解し、複数のプランがある場合は、機能やサポート内容の違いが一目でわかる比較表を用意します。
その際、最も推奨するプランを視覚的に強調すると効果的です。価格だけでなく、導入によって「どれだけの工数が削減できるか」といった費用対効果(ROI)のモデルケースを示すことで、価格の妥当性を伝え、納得感を醸成します。
5. 導入事例一覧ページ
導入事例は、見込み顧客がサービス導入後の成功イメージを掴み、「自分ごと化」を促進するための強力なコンテンツです。一覧ページでは、業種、企業規模、課題といった軸で事例を絞り込めるようにし、ユーザーが自身と近い境遇の企業を簡単に見つけられるUIを設計します。
各事例のタイトルには「〇〇の導入でコストを30%削減」のように、具体的な成果や改善指標を入れることで、詳細ページへのクリック率を高めます。
6. 導入事例詳細ページ
事例詳細ページでは、まず冒頭に「企業概要」「導入の背景・課題」「成果の要約」などをまとめた概要ボックスを設置し、読者が短時間でポイントを掴めるようにします。本文は「課題 → 解決策のアプローチ → 成果 → 今後の展望」といったストーリーで構成し、実際の担当者のコメント(お客様の声)や成果を示すグラフなどを盛り込むことで、内容の信頼性を高めます。
記事の要所や末尾には、関連サービスへのリンクや資料ダウンロード、問い合わせといったCTAを配置し、高まった興味を行動へと転換させます。
7. 資料ダウンロード一覧ページ
資料ダウンロード一覧ページの目的は、訪問者が求める資料を「探す手間を最小限に」し、効率的に入手できるようにすることです。
「サービス紹介資料」「導入事例集」「お役立ちホワイトペーパー」のようにカテゴリ分けを行い、各資料カードには、対象読者や資料から得られる知見、ページ数などを明記して、ダウンロードする価値が事前にわかるように設計します。関連資料へのリンクを設置し、ユーザーの連続的な情報収集を促すことも有効です。
8. 資料ダウンロード入力ページ
フォームは、見込み顧客情報を獲得するための重要なページですが、最も離脱されやすいポイントでもあります。デザインの原則は「一貫性・最小負担・離脱抑止」です。どの資料のフォームか分かるようにタイトルを揃え、ヘッダーやフッターの不要なリンクは削除して入力に集中させます。
入力項目は必要最小限に絞り、「必須」「任意」を明確に区別します。リアルタイムでの入力チェック(バリデーション)機能を実装し、送信ボタンが押せない理由を分かりやすく示すなど、ユーザーのストレスを極限まで減らす工夫が求められます。
9. 資料ダウンロード完了ページ
完了ページ(サンクスページ)では、「ダウンロードが成功したこと」を明確に伝えた上で、「次の行動」を提示することが重要です。目立つ位置にダウンロードボタンを配置し、すぐに資料が手に入ることを示します。
さらに、「この資料を読んだ方へのおすすめコンテンツ」として、関連性の高い別資料や導入事例、セミナー情報などを提示することで、サイト内での回遊を促し、顧客の検討段階をさらに深めることができます。
10. お問い合わせ入力ページ
お問い合わせフォームも、資料ダウンロードフォームと同様に、ユーザーの負担を最小限に抑える設計が基本です。可能であれば1ページで完結させ、項目が多い場合は進捗がわかるステップ表示(インジケーター)を設置してユーザーの不安を軽減します。
自由記述欄を減らして選択式の項目を多用したり、問い合わせ種別(製品に関するお問い合わせ、協業に関するご相談など)を選択できるようにしたりすることで、ユーザーの入力負荷を下げると同時に、社内の担当者へのスムーズな振り分けが可能になります。
11. お問い合わせ完了ページ
お問い合わせ完了ページで最も重要なのは、ユーザーの「送信後の不安」を解消することです。「お問い合わせありがとうございます」という感謝のメッセージとともに、「いつまでに(例:3営業日以内に)」「誰から」「どのような手段で(メールまたは電話で)」連絡が来るのかを具体的に明記します。
これにより、ユーザーは安心して返信を待つことができます。返信を待つ間に役立つFAQページへのリンクや、お役立ち資料への導線を設置し、関心が高まっているうちに関係性を維持する工夫も効果的です。
BtoBサイト制作のワイヤーフレーム&チェックリスト
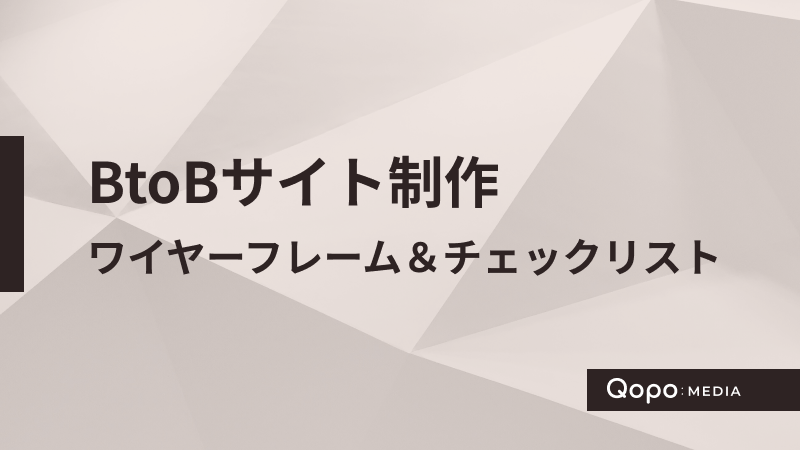
ここまでBtoBサイトの主要ページのデザインのポイントを解説してきました。Qopoではこれらのポイントを反映した、BtoBサイトのワイヤーフレームと、制作時に押さえておきたいポイントをまとめたチェックリストを用意しています。自社のBtoBサイトと照らし合わせながら、サイト改善の参考としてご活用ください。
BtoBサイト制作における参考デザイン集
これまでBtoBサイト制作におけるデザインの重要性や、各ページのポイントを解説してきました。しかし、実際にデザインを進める上では、優れた他社サイトから自社サイトの着想を得ることも非常に重要です。
優れたWebデザインのアイデアやインスピレーションを探せる参考サイト集「PixPicks」では、BtoBカテゴリに特化した優れたデザインのサイトも多数掲載されています。
各社のメッセージの伝え方、導線設計、情報の見せ方などを比較することで、自社の強みをより効果的に伝えるためのヒントが得られるはずです。ぜひ、自社サイトの制作やリニューアルの参考としてご活用ください。
まとめ
本記事では、BtoBサイトにおけるデザインの重要性から、主要ページごとの具体的なポイントまでを網羅的に解説しました。
BtoBサイトのデザインは、単なる見た目の美しさを追求するものではなく、事業戦略を成果に結びつけるための「論理的な仕組み」です。多くの意思決定者が関わる長期的な検討プロセスにおいて、顧客が抱える課題を深く理解し、その解決策を分かりやすく提示することで信頼を獲得することが求められます。
ご紹介した各ページのポイントやチェックリストなどを参考に、ぜひ自社のWebサイトが「顧客の合理的な判断を支えるパートナー」として機能しているかを見直してみてください。戦略に基づいたデザインは、顧客との強固な信頼関係を築き、ビジネスを成長させるための強力な資産となるはずです。
BtoBサイト制作なら、Qopoにご相談ください
私たちは、BtoBマーケティングの戦略支援・Webサイト制作に強みを持つ会社です。BtoB領域の豊富な知見を活かし、「制作のための制作」ではなく、「成果創出」に徹底してこだわるスタイルが特徴です。BtoBサイトの制作や改善、リニューアルをご検討の方は、是非、ご相談ください。